英語偏差値30からカナダ東海岸St.Thomas Universityに留学。卒業後2009年4月、某財閥系総合商社へ入社。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
さて、リクエストがいくつか来た。考えてみれば、ESもESのシーズンになって急に質問が増え始めて、面接に関する質問もこれからかなり増えてくるだろうと思われる。
ので、今回は面接を受ける際の注意点について纏めておく。
結局のところ、面接は基本的に事前に提出したESをもとに行われるのだし、自分はESは面接官と就活生のリンクが大事だと考える。なので、特に注意する点はESとほとんど同じ。
ただ、面接はface to faceで実際に自分の考えを相手に分かりやすく伝えなければならないし、ESと違って集団面接のように他の就活生を強く意識しなければならない場面にも多々出くわす。その点も踏まえてポイントを以下に纏める。

<面接の際に気を付けること>
①「文章」と「言葉」の違いを意識する
自分の言葉で伝える、ということ。
ESで書いたことについて面接ではもう一度聞かれることが多いのだけど、それを読み上げるようにそのまま言ってはいけない。ESでは相手に伝える文章、面接では言葉で、場面が違うのだから伝え方も違う。それぞれ最適な方法で表現すべき。
Norm Chomskyが書く論文が恐ろしく難解でも彼のスピーチは非常に明快で面白いし、優秀なしばしば人間は自分の複雑な考えを相手に分かりやすく伝えることに長けている(残念ながら政治科学者には少ないのだが)。
こんな至極当たり前のことをわざわざ『』付きで強調したのは、これが出来ていない人が余りにも多かったから。「自己PRをしてください」と聞かれてESに書いたようなことをそのまま読み上げたり、事前に練習してきたようなフレーズをリピートしているような人が本当に多かった。
ここに気付かない人は、自己PRやエピソードは何とか話せたとしても、ちょっと面白い質問(無茶振り)には大抵答えられない。
ジェスチャーを交えるなり、「実はまだまだこんな面白いことがあって・・・」と自分らしい会話の切り出し方をするなり、面接こそ自分らしさを最大限に発揮するもの。
②面接後の反省を必ずノートに纏める
これも必須。面接に受かろうが落ちようが、必ず面接の後に反省をする。ESの時点での反省の効果は見えずらいが、面接の場合はすぐに結果に表れる。
面接官の印象はどうか、どんな質問をされたのか、どんな答えに手ごたえを感じたのか、どんな答え方がまずかったのか、どんなジェスチャーが良かったのか、なぜ受かったのか、なぜ落ちたのか、どの学生の印象が良かったか、など、思い出せることは全て思い出して反省する。
そこからどういった能力・視点・雰囲気を求めているのか、などなど、帰納的に考えられることを洗い出しよく考え、次の面接に反映する。
面接で聞かれることなんて本当に限定されたことなので、これを繰り返しているうちに面接に余裕が出て来、落ちなくなる。
考えてみたのだけど、以上の2点くらいしか書くほど重要な注意点が見つからない。やはり前回書いた、自分自身をHowとWhyで追求することが一番重要だと思うし、それが面接になったところで、基本的なところは何も変わらない。
ESと面接の一番の違いは、当然のように「文章」と「言葉」。この違いが何を意味するのか、自分なりに考えれば、上記の2点のような、最も基本的なポイントに行き着くのでは、と思う。
これからますます忙しくなる就職活動、頑張ってください。
imayu
Picture:
<http://
ので、今回は面接を受ける際の注意点について纏めておく。
結局のところ、面接は基本的に事前に提出したESをもとに行われるのだし、自分はESは面接官と就活生のリンクが大事だと考える。なので、特に注意する点はESとほとんど同じ。
ただ、面接はface to faceで実際に自分の考えを相手に分かりやすく伝えなければならないし、ESと違って集団面接のように他の就活生を強く意識しなければならない場面にも多々出くわす。その点も踏まえてポイントを以下に纏める。
<面接の際に気を付けること>
①「文章」と「言葉」の違いを意識する
自分の言葉で伝える、ということ。
ESで書いたことについて面接ではもう一度聞かれることが多いのだけど、それを読み上げるようにそのまま言ってはいけない。ESでは相手に伝える文章、面接では言葉で、場面が違うのだから伝え方も違う。それぞれ最適な方法で表現すべき。
Norm Chomskyが書く論文が恐ろしく難解でも彼のスピーチは非常に明快で面白いし、優秀なしばしば人間は自分の複雑な考えを相手に分かりやすく伝えることに長けている(残念ながら政治科学者には少ないのだが)。
こんな至極当たり前のことをわざわざ『』付きで強調したのは、これが出来ていない人が余りにも多かったから。「自己PRをしてください」と聞かれてESに書いたようなことをそのまま読み上げたり、事前に練習してきたようなフレーズをリピートしているような人が本当に多かった。
ここに気付かない人は、自己PRやエピソードは何とか話せたとしても、ちょっと面白い質問(無茶振り)には大抵答えられない。
ジェスチャーを交えるなり、「実はまだまだこんな面白いことがあって・・・」と自分らしい会話の切り出し方をするなり、面接こそ自分らしさを最大限に発揮するもの。
②面接後の反省を必ずノートに纏める
これも必須。面接に受かろうが落ちようが、必ず面接の後に反省をする。ESの時点での反省の効果は見えずらいが、面接の場合はすぐに結果に表れる。
面接官の印象はどうか、どんな質問をされたのか、どんな答えに手ごたえを感じたのか、どんな答え方がまずかったのか、どんなジェスチャーが良かったのか、なぜ受かったのか、なぜ落ちたのか、どの学生の印象が良かったか、など、思い出せることは全て思い出して反省する。
そこからどういった能力・視点・雰囲気を求めているのか、などなど、帰納的に考えられることを洗い出しよく考え、次の面接に反映する。
面接で聞かれることなんて本当に限定されたことなので、これを繰り返しているうちに面接に余裕が出て来、落ちなくなる。
考えてみたのだけど、以上の2点くらいしか書くほど重要な注意点が見つからない。やはり前回書いた、自分自身をHowとWhyで追求することが一番重要だと思うし、それが面接になったところで、基本的なところは何も変わらない。
ESと面接の一番の違いは、当然のように「文章」と「言葉」。この違いが何を意味するのか、自分なりに考えれば、上記の2点のような、最も基本的なポイントに行き着くのでは、と思う。
これからますます忙しくなる就職活動、頑張ってください。
imayu
Picture:
<http://
PR
ここのところ、エントリーシートに関する質問をかなりの数で受けているので、ここに簡単に纏めておこうと思う。ESの考え方や書き方は人によって違い、それぞれの考察に立脚したESこそが素晴らしいESになるのだと思うのだが、参考までにここに自分の考えていた点を中心に書いておく。

Picture: RandallHMiller
<ESを書くにあたって気を付けること>
①自分の入りたい業界・会社の求める能力を自分なりに纏める
せっかく魅力的な自己PRや強みを書くことができても、そこでアピールする能力が、会社と業界の求める能力からかけ離れたものであっては意味がない(ex. マスコミに銀行的従順さ・堅実さをアピール)。まず、社長のコメントなり、会社のパンフレットなり、ウェブなり、社員さんの話を聞くなり、自分なりに情報収集して、その会社・業界がどんな能力を求めているのかを明確にする。
②自分のエピソードをHowとWhyで追求する
ある決断をした時や行動を起こした時、頑張った時など、自分はなぜそう思ったのか、どのようにそれを行ったのか、どうやって目標を達成したのか、その背景にある哲学や価値観をとことん追求する。その結果見えたものが、今までの自分の行動の基軸。そこから自分らしさや自分の持つ能力・強みを見つけ出すことができれば、どんな質問がきても答えられる。
ちなみに、留学生活で得られた大きなことの一つは、この追求する姿勢だと思う。
③自分の能力を用いて仕事でどう活かせるかを具体化する
②で考え抜いた自分の強みを、①で調べ抜いた会社の求める能力に落とし込み、そこで働いている自分を具体的なイメージに落とし込む。どんな業務に就きたいのか、3年・5年・10年後何をしているか、自分の目標に近づけているか、その際の業務を遂行する際に自分の強みをどう活かしているか、出来るだけ具体的なイメージを描けるようにする。そうすれば、自分自身(自分の強み・哲学・軸)と面接官(会社での業務)のリンクが出来、面接官に自分自身が伝わるようになる。
④自己PRの構成を考える
会社・業界の求める能力と自分の能力と軸が分かったら、あとは自己PRという枠に出来るだけ伝わりやすくなるように落とし込むのに。自己PRについては、「強み(端的に)*それを証明するエピソード*まとめ(その強みをどう業務に活かせるか)」の3段落締め、といった王道パターンをはじめとして様々な構成が考えられるが、自分の強みが一番伝わりやすい構成を自分なりに考えられれば最高。
その他にも、分かりやすいキャッチフレーズを作る、比喩を用いる、【】<>『』などの記号を使うなど、自分なりに工夫して、自分らしさ溢れるESを作ることができる。
以上の4つの点に気を付ければ、会社の求める能力と自分の強みをリンクさせ、面接官にも具体的イメージを喚起させやすい良いESができると思う。
特に②は重要で、いわゆる「自己分析」にかなり近い部分もあると思うのだけど、HowとWhyで自分をどれだけ深くまで探求・理解してブレない軸を持つことができるかが、ESだけでなく就職活動自体を満足に行うことができるかどうかの鍵なのでは、と思う。
面接編もこれからリクエストがあれば書こうと思います。
Imayu
Picture: RandallHMiller
<ESを書くにあたって気を付けること>
①自分の入りたい業界・会社の求める能力を自分なりに纏める
せっかく魅力的な自己PRや強みを書くことができても、そこでアピールする能力が、会社と業界の求める能力からかけ離れたものであっては意味がない(ex. マスコミに銀行的従順さ・堅実さをアピール)。まず、社長のコメントなり、会社のパンフレットなり、ウェブなり、社員さんの話を聞くなり、自分なりに情報収集して、その会社・業界がどんな能力を求めているのかを明確にする。
②自分のエピソードをHowとWhyで追求する
ある決断をした時や行動を起こした時、頑張った時など、自分はなぜそう思ったのか、どのようにそれを行ったのか、どうやって目標を達成したのか、その背景にある哲学や価値観をとことん追求する。その結果見えたものが、今までの自分の行動の基軸。そこから自分らしさや自分の持つ能力・強みを見つけ出すことができれば、どんな質問がきても答えられる。
ちなみに、留学生活で得られた大きなことの一つは、この追求する姿勢だと思う。
③自分の能力を用いて仕事でどう活かせるかを具体化する
②で考え抜いた自分の強みを、①で調べ抜いた会社の求める能力に落とし込み、そこで働いている自分を具体的なイメージに落とし込む。どんな業務に就きたいのか、3年・5年・10年後何をしているか、自分の目標に近づけているか、その際の業務を遂行する際に自分の強みをどう活かしているか、出来るだけ具体的なイメージを描けるようにする。そうすれば、自分自身(自分の強み・哲学・軸)と面接官(会社での業務)のリンクが出来、面接官に自分自身が伝わるようになる。
④自己PRの構成を考える
会社・業界の求める能力と自分の能力と軸が分かったら、あとは自己PRという枠に出来るだけ伝わりやすくなるように落とし込むのに。自己PRについては、「強み(端的に)*それを証明するエピソード*まとめ(その強みをどう業務に活かせるか)」の3段落締め、といった王道パターンをはじめとして様々な構成が考えられるが、自分の強みが一番伝わりやすい構成を自分なりに考えられれば最高。
その他にも、分かりやすいキャッチフレーズを作る、比喩を用いる、【】<>『』などの記号を使うなど、自分なりに工夫して、自分らしさ溢れるESを作ることができる。
以上の4つの点に気を付ければ、会社の求める能力と自分の強みをリンクさせ、面接官にも具体的イメージを喚起させやすい良いESができると思う。
特に②は重要で、いわゆる「自己分析」にかなり近い部分もあると思うのだけど、HowとWhyで自分をどれだけ深くまで探求・理解してブレない軸を持つことができるかが、ESだけでなく就職活動自体を満足に行うことができるかどうかの鍵なのでは、と思う。
面接編もこれからリクエストがあれば書こうと思います。
Imayu
前回の続きです。
今回は田母神さんは息を潜め、もっぱら政治科学と歴史学の話になります。
さて、田母神氏の歴史観に関する主張を読んでみて、歴史観を変える・提唱することの難しさをつくづく感じた先日。歴史的事象なんて星の数ほどあって、それらを差別的に集めてきて自分の擁護する歴史観を説明するための証拠とすればいい。しかもその記録されてきた歴史自体も、編纂者の意向が反映されていて歴史の「真実」を伝えている可能性は限りなく低い。
だから俺の歴史学の教授は、
''We never know about history, but history is all about understanding it.''
「完全に歴史を知ることは出来ないけれど、それを理解する事こそが歴史学だ」
と言ったんだね。歴史について確固たる資料や事実をもって「知る」ことは出来ないけれど(確固たる歴史観は無い)、その時代背景や価値観などを調べることによって、「理解」を高めることはできる、と。
だけれどこの考え方、俺のお世話になった政治科学部の教授達のアプローチと真っ向から対立する。
Political Science、政治科学、ポリサイ。
俺の大学だけではなく、欧米では至極ポピュラーなこの学問の名前、考えてみるとどこかおかしい。なぜ、「政治学(Politics)」ではなく、「政治科学(Political Science)」なのか。ここに政治学者達の自負心と信条、そして歴史学者達との軋轢の根源がある。
まず言ってしまおう。「(政治)学」、と「(政治)科学」、の違いは、前者は、事実を学ぶことであって、後者は、物事(の因果関係)を仮定し、検証し、一般化(Theorize, Generalize)し、更には物事の予測を可能にする、という点。
政治の仕組みや働きなどを勉強して知識にするのは政治学、そして、政治科学は、その山ほどある政治的事象を検証、一般化し、その上に政治理論を作り上げる。
例えば、「AとBという政治的現象が観測されたら、Cが起こる」という感じ。具体的な例を挙げると、経済混乱+沢山の労働階級+民族のバラエティ+民主主義(!!!)=ナチズムの台等の懸念、のようなもの。
更に政治科学の、科学的・数字的側面を強調していくと、デベルジェ(Duverger)のMedian Voter Theoryやライカー&オードシュック(Riker&Ordeshook)の投票行動方程式なんてのがある。
----------------------------------------------------------
※参考までに
投票行動方程式
R= P x B - C + D
R=選挙に行く可能性
P=1人の投票が結果を変える可能性(要は接戦かどうかって事)
B=投票する政党、又は立候補者を変える事による結果の変化
(それぞれの政党、立候補者の間でどれだけの違いがあるか)
C=投票に行く事によるコスト(時間、仕事、いろいろ)
D=選挙に行く事で得られる満足感。
以前にも紹介した覚えがありますが。
面白いでしょ?あ、そうでもない?…w
----------------------------------------------------------
水素に火を点けたら水になりますよ(H2+O=H2O)という確固たる因果関係を見つけだす化学のように、政治科学も、事象と事象の確固たる因果関係を見つけ出し、理論化しようとする。
ちょっと待った。ここでウチの歴史学者が口を出す。「過去に起こった事象なんてそれぞれの時代背景が余りにも特有過ぎて、現代に当てはめることなんて不可能だ。」「政治科学者こそ、自分の論理に都合のいい事象だけを掻き集めてきて論証しているだけじゃないか。」と言う。
この歴史学者は、歴史的事象の特有性について細心の注意を払い、そこから因果関係を導き出すなんて不可能だと言う。
しかしここで政治科学者も黙ってはいない。彼らには、過去の失敗や政治システムの研究によって、国や世界の危機を未然に防いだり、より良い政治システム作りに貢献しようという自負がある。悪い結果を引き起こす事象を特定できれば失敗を防げる。そしていい結果をもたらす事象を発見できれば将来より良いシステムが作れる。
この自負を捨ててしまえば、プラトンやアリストテレスの時代から続いてきた政治科学者の役目が終わってしまうので、それは絶対に認めない。
こんな中で俺がいつも思っていたのは、結局歴史学者も政治化学者も似たような問題を抱えてるんじゃないか、ってこと。歴史学と政治科学は本来「哲学」という学問の中に共存していたはずだし、それを無理に引き離そうとすれば、お互いが独立して存在するために様々なアプローチを考え出すだろう。
歴史学者だって歴史における普遍的法則を見つけ出そうとするだろうし(ダーウィンの進化論とかね)、政治科学者が政治的事象をより深く理解しようとするアプローチだってある(もっとも、そうすればただのの政治学になってしまうのだけど)。
歴史学者が歴史を「理解」することに重きを置けば、政治科学者は政治の普遍的法則を「知ろう」とする。結局どちらも同じようなジレンマを抱えて存在しているんじゃないか。
ただ、歴史学者が歴史科学者、と名乗らないところを見ると、歴史学者は科学的アプローチを放棄したかのようにも見える。ひょっとしてそれは、「歴史」そのものを尊重する姿勢の現れなのかもしれない。
一方で政治科学者にもおかしなところがある。Political Scientistであるために、政治的法則を発見したいがために、この現実世界を捻じ曲げることが多々ある。膨大な社会現象全てを踏まえて理論を立てるのは難しいので、経済学のように次々に前提を作って、その上に理論を立てる(例えば、「国民はそれぞれ個人の利益を最大化する為に行動する、と仮定する」「国民は、自分で仕組みを作り出すのではなく、作り出された仕組みに影響される、と仮定する」など)。
理論作りに躍起になっている政治科学者は、彼ら本来の目的、「よりよい社会、政治システムを作る」という目標から遠ざかっているようにも思える。「どんな社会が良い社会か」「どんな政治システムが良いものか」という根本的質問を哲学に丸投げして、政治科学本来の存在意義を見失っているのでは?
歴史学と政治科学、お互いの存在を維持するための軋轢を維持するのでは無く、その中でお互いが見落としている点を補完しあってこそ、よい結果が生まれるのではないのかな(大きくは無いが、この動きも無いことはない)。
もっとも、もしもそんな事が本格的に起こってしまったら、社会科学上の大変革になってしまうんだけど。
キリが無い。もう止めようw
田母神さんの本から思いがけず、懐かしい大学生活を思い出した。
Picture: Raphael
最近は更新が滞ってしまって申し訳ないです。
去年牧場から期間して以来、友達の大切さを再確認しましてミクシィを始めまして。
その2つの定期的な更新維持はなかなか難しく、こちらのブログが止まり気味になってしまいました。
ミクシィの内容と重なることも多いのですが、こちらにもUPしていきます。
-------------------------------------------------------------------------------------
田母神前航空幕僚長の『自らの身は顧みず』を、
今更ながらざっと読んでみた。
この本は今回のエントリーの主題ではないので詳しい内容は割愛するけど(参考リンク)、要するに彼が言いたいのは、「日本は歴史的な過ちなど犯していない、すなわち侵略国家ではないのだから、日本の誇りと主体性を取り戻しなさいよ」ということ。
①南京虐殺は実際には行われていない
②真珠湾攻撃はコミンテルンの策略だった
③日本兵は常に国際法を遵守していた etc.
にも関わらず日本がこれほどの自虐史観を持つのは、東京裁判とそれ以降の占領で列強諸国がそれを植えつけたから、だと。
彼の主張も的を射ているところは多々あるし、国体への問題提議、という意味では有益な本だと思うけど、俺が何より感じたのは、「歴史観を変える、または新しい歴史観を説得力を持って提示するのって本当に難しいな」ということ。
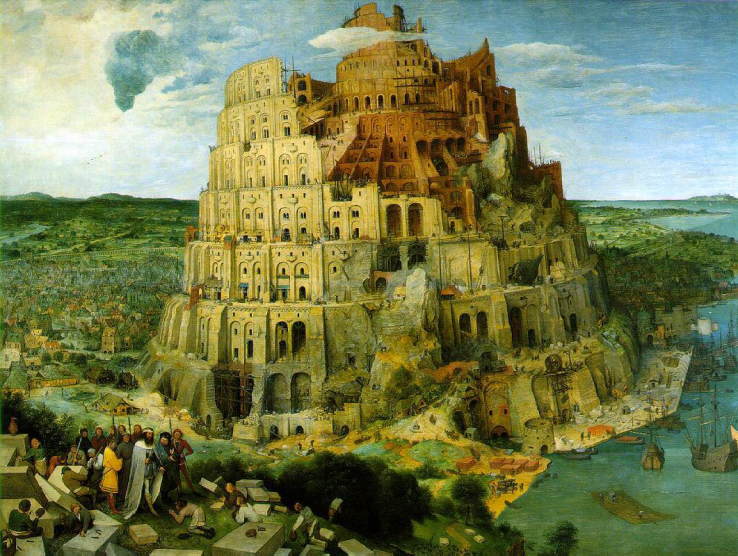
Pieter Prueghel
俺の専攻は歴史学ではないので、詳しいパラダイムシフトなどを踏まえて説明することは出来ないのだけど、歴史なんて言ってみれば見方によってどうとでもなる。
南京虐殺について、田母神さんが上記のような主張をする一方、「南京虐殺では30万人殺された」とか、「実は10万人だった」(中道派、なんて言い方をしたりする)とか、色んな意見がある。それぞれの主張をサポートするための資料を片っ端から選んで集めてくれば、どんな主張でも作り上げることができる。
違う「歴史」を見てみよう。9.11、イラク戦争時(今も)のイスラム教に対するイメージ・歴史観は、「排他的」「原理主義的」「ジハードの概念が危険」というものだった。
特にジハードを例に取ってみる。「ジハードはイスラム教徒に他宗教を弾圧する正当性を与える」、「ジハードは非人道的」、という歴史観を作り出したければ、
①リコンキスタ時代のアンダルシアでは、ジハードは戦争を仕掛けることを正当化するために解釈された
②十字軍との衝突の時代では、ジハードは兵隊確保、捕虜の処分のために、奴隷制度、死刑制度、税制度を整備する際に多様に解釈された
③近代では、パキスタンの独立や領土拡大のための戦争を正当化するためにジハードは解釈された
④ビン・ラディンは、アメリカを十字軍に見立ててそれの迎撃を正当化するためにジハードを解釈した etcetcetc....
と、ジハードが戦争を正当化した例をイスラム1500年の歴史から片っ端から集めればいい。
逆に、「イスラムは平和な宗教なんだ」「他宗教との共存も認めている」と主張したければ、
①ムハンマドはメディーナでの布教に際して、現地のユダヤ人との共生を計ったが拒否された
②アバシッド時代では、イスラム政府の高官にユダヤ人を積極的に登用していた
③コーランには、'people of the book'という、他宗教を認める項目がある etcetcetc...
と、イスラム教が他宗教と共存していた、しようとしていた例を片っ端から集めればいい。
なので、一つの歴史観にまとまることなんてありえないし、ある歴史観が他の歴史観よりも正しい、なんて主張することも不可能に近い。
より多くの資料と説得力のある情報源を携えた主張が一番正しいのかもしれないけど、そのためには、その資料がどれだけ信用できるか、をまず議論しなければならない。そこで明確な基準を示すことも不可能。
更には、そんな昔から現代に残っている歴史書が公正にその時代を記述してあるのか、といえばそうではない。日本書紀が別名藤原史観と呼ばれるように、ローマ帝国時代の文献であればそれを正当化するような記述に傾倒しているだろう。誰でも好きなように歴史を記録できる現代ならまだしも、限られた人しか文字を使えなかった昔であれば尚更のこと。その時代ごとに違った時代背景があるのに、それを想像しえない現代人が、その時代の資料だけに基づいて歴史を理解し、歴史観を作る、なんて本当に出来るのか。
だから、歴史観に説得力を持たせるのは物凄く難しいんだね。
でも、だからこそ、歴史学というのは、その時代に何が起こったのかについて、より深い理解と、説得力のある説明を追い求めるロマンがあるのかもしれない。
俺が大学4年の時に唯一取った歴史学の教授が言っていたことを思い出す。
''We never know about history, but history is all about understanding it.''
完全に歴史を知ることは出来ないけれど、それを理解する事こそが歴史学だ、と。
うーん、なるほど。
※田母神さんの話に少し戻る。彼は、近代日本の歴史観を書いているので、資料に基づいた論証が比較的しやすかったはず。それでも彼は著書の中でその情報源をロクに提示していないので論外。
ここでふと、政治科学と歴史学は非常に仲が悪い、ということを思い出した。
つづく。
Imayu
それでも歴史大好き!→
去年牧場から期間して以来、友達の大切さを再確認しましてミクシィを始めまして。
その2つの定期的な更新維持はなかなか難しく、こちらのブログが止まり気味になってしまいました。
ミクシィの内容と重なることも多いのですが、こちらにもUPしていきます。
-------------------------------------------------------------------------------------
田母神前航空幕僚長の『自らの身は顧みず』を、
今更ながらざっと読んでみた。
この本は今回のエントリーの主題ではないので詳しい内容は割愛するけど(参考リンク)、要するに彼が言いたいのは、「日本は歴史的な過ちなど犯していない、すなわち侵略国家ではないのだから、日本の誇りと主体性を取り戻しなさいよ」ということ。
①南京虐殺は実際には行われていない
②真珠湾攻撃はコミンテルンの策略だった
③日本兵は常に国際法を遵守していた etc.
にも関わらず日本がこれほどの自虐史観を持つのは、東京裁判とそれ以降の占領で列強諸国がそれを植えつけたから、だと。
彼の主張も的を射ているところは多々あるし、国体への問題提議、という意味では有益な本だと思うけど、俺が何より感じたのは、「歴史観を変える、または新しい歴史観を説得力を持って提示するのって本当に難しいな」ということ。
Pieter Prueghel
俺の専攻は歴史学ではないので、詳しいパラダイムシフトなどを踏まえて説明することは出来ないのだけど、歴史なんて言ってみれば見方によってどうとでもなる。
南京虐殺について、田母神さんが上記のような主張をする一方、「南京虐殺では30万人殺された」とか、「実は10万人だった」(中道派、なんて言い方をしたりする)とか、色んな意見がある。それぞれの主張をサポートするための資料を片っ端から選んで集めてくれば、どんな主張でも作り上げることができる。
違う「歴史」を見てみよう。9.11、イラク戦争時(今も)のイスラム教に対するイメージ・歴史観は、「排他的」「原理主義的」「ジハードの概念が危険」というものだった。
特にジハードを例に取ってみる。「ジハードはイスラム教徒に他宗教を弾圧する正当性を与える」、「ジハードは非人道的」、という歴史観を作り出したければ、
①リコンキスタ時代のアンダルシアでは、ジハードは戦争を仕掛けることを正当化するために解釈された
②十字軍との衝突の時代では、ジハードは兵隊確保、捕虜の処分のために、奴隷制度、死刑制度、税制度を整備する際に多様に解釈された
③近代では、パキスタンの独立や領土拡大のための戦争を正当化するためにジハードは解釈された
④ビン・ラディンは、アメリカを十字軍に見立ててそれの迎撃を正当化するためにジハードを解釈した etcetcetc....
と、ジハードが戦争を正当化した例をイスラム1500年の歴史から片っ端から集めればいい。
逆に、「イスラムは平和な宗教なんだ」「他宗教との共存も認めている」と主張したければ、
①ムハンマドはメディーナでの布教に際して、現地のユダヤ人との共生を計ったが拒否された
②アバシッド時代では、イスラム政府の高官にユダヤ人を積極的に登用していた
③コーランには、'people of the book'という、他宗教を認める項目がある etcetcetc...
と、イスラム教が他宗教と共存していた、しようとしていた例を片っ端から集めればいい。
なので、一つの歴史観にまとまることなんてありえないし、ある歴史観が他の歴史観よりも正しい、なんて主張することも不可能に近い。
より多くの資料と説得力のある情報源を携えた主張が一番正しいのかもしれないけど、そのためには、その資料がどれだけ信用できるか、をまず議論しなければならない。そこで明確な基準を示すことも不可能。
更には、そんな昔から現代に残っている歴史書が公正にその時代を記述してあるのか、といえばそうではない。日本書紀が別名藤原史観と呼ばれるように、ローマ帝国時代の文献であればそれを正当化するような記述に傾倒しているだろう。誰でも好きなように歴史を記録できる現代ならまだしも、限られた人しか文字を使えなかった昔であれば尚更のこと。その時代ごとに違った時代背景があるのに、それを想像しえない現代人が、その時代の資料だけに基づいて歴史を理解し、歴史観を作る、なんて本当に出来るのか。
だから、歴史観に説得力を持たせるのは物凄く難しいんだね。
でも、だからこそ、歴史学というのは、その時代に何が起こったのかについて、より深い理解と、説得力のある説明を追い求めるロマンがあるのかもしれない。
俺が大学4年の時に唯一取った歴史学の教授が言っていたことを思い出す。
''We never know about history, but history is all about understanding it.''
完全に歴史を知ることは出来ないけれど、それを理解する事こそが歴史学だ、と。
うーん、なるほど。
※田母神さんの話に少し戻る。彼は、近代日本の歴史観を書いているので、資料に基づいた論証が比較的しやすかったはず。それでも彼は著書の中でその情報源をロクに提示していないので論外。
ここでふと、政治科学と歴史学は非常に仲が悪い、ということを思い出した。
つづく。
Imayu
それでも歴史大好き!→
新年の抱負。
前回、2008年を振り返ってみて、
自分に改めて必要なことが沢山見えてきた。
なので今回はそれを踏まえて2009年の抱負にしようと思います。

以前のエントリーでも書いたけど、
自分の場合、大学一年の時から常に意識していることがあって、
それを毎年の行動の指針にしている。
(一年生の終わりの期末論文でこの原則を熱く書いたな~そういえば)
それは、自分の「やりたいこと」、「すべきこと」、「できること」、
の3つを念頭において、本当に自分が今すべきことを実行する、ということ。
これは、自分がどんな目標に向かってどこにいて何をしているか、
を認識するのにとても役に立ってきた。
ところで、就活の時に気づいたのだけど、
とある会社もこの3原則を社訓としていた。
俺の方が先だ。
このImayu3原則は常に心に留めておくこととして、
今年は3つの言葉をキーワードに、抱負にしようと思う。
キーワードは、「信頼」、「客観」、「実践」。
①信頼 Trustfulness
今年は、人との繋がりの大切さを心底感じた年だった。その繋がりにいつも助けられたし、迷っている時にも背中を押してもらいました。逆に、大学を卒業する際に、お世話になった先生方に十分な挨拶をせずに帰国してしまった、という悔やまれることがある。加えて、今年からはいよいよ入社ということで、人との信頼関係がより一層大切になってくるはず。
なので、時間のあるこの年、この機会に、今まで不十分だったと思う挨拶などをきっちり済ませ、新たなスタートとしたい。(さぁ~大変だ!)
そして、人から背中を押された分、自分も人の背中を押して上げられるような、そして信頼されるような人間を目指そう。また、信頼構築がより重要になる会社生活を意識して、信頼をむしろ勝ち取るような人間になりたいと思う。
これには、メールだったり手紙だったり電話だったり、細々したことを面倒くさがらずマメにやっていくことが大事だと思うけど、他にもブログであったり、SNSであったり、Web2.0も含めたあらゆる面に敏感になって、自分を発信して相互理解ができればな、と思っています。せっかくミクシィも始めたしね。
②客観 Objectivity
これはImayu3原則の中に既に含まれているけど、自分を客観的に見つめて行動したい、ということ。
2008年は、自分の信念や夢に従って知的好奇心を追求していったぶん、それに熱くなり過ぎて他の事があまり見えなくなってしまったと思う。その結果、自分の考えに確信を持つこともできたけど、そうする内に、そのマイナス面や、逆の視点まで考えが至らないことが多々あった。
マイクロクレジットにしても、マイクロファイナンスにしてもそう。様々な方法で途上国貢献を実現している光景を目の当たりにして心酔してしまい、客観的な視点を欠いてしまった。その度に色んな人にハッとさせられて考えさせられて。
2009年は、これからは、こういうことを無くして行きたい。政治科学を取っていた時、その問題点に気づいて人権学も勉強し始めたじゃないか。日本での留学プレゼンだって、留学生の視点だけで物事を言っていてはダメだと気づいて、日本の大学に潜入調査に行って来たじゃないか。こういう客観的な観点こそが、自分を支えてきたコアだということを忘れていた。
自分の夢を実現する時こそ、大きく環境が変化する2009年こそ、こういう客観的な視点を忘れずに、物事の問題点を冷静に認識して、それを改善できるように努力していきたい。
2009年は絶対に、客観的視点を忘れない!
③実践 Practicality
大きな環境の変化に晒されるであろう2009年、学生時代とは違った実践性が求められるのだろうと思う。特にこれからはビジネスの世界に足を踏み入れるので、学生時代に培ってきた考え方を実践分野にうまく転換していかなければならないと思う。具体的な例で言えば、ビジネスオケージョンにおけるロジカルシンキングとか財経理税務会計とかコーポレートファイナンスとか。
short term goalとlong term goal、その2点を視野に入れて、よく考えて、今すべきこと、できることを明確にして、キチンと実践していきたい。
この3つを今年の目標にしよう。
みんな、もし俺がこれらを怠っていたら、遠慮なく指摘してください。
ブログで宣言してしまったのでもう逃げられないw
具体的な目標、成果はおいおい書いていきたいな。
今年厄年だろうが何だろうが、全力で駆け抜けてやる。
あとは本を沢山読むことと、ドラムやファッションとか他の事にも手を抜かないこと。1~2日に1冊のペースは維持して行きたいし、リラックスして、色んなことにチャレンジして視野を広げていきたい。考え方が凝り固まってしまってもいけない。まず、入社までに、新潮文庫のパンダのブックカバーを2つゲットして。。。
ということで、みなさん今年も宜しくお願い致します。
2009年も、頑張っていきましょう!
Imayu
2009年、同じく厄年の人wあららw→
前回、2008年を振り返ってみて、
自分に改めて必要なことが沢山見えてきた。
なので今回はそれを踏まえて2009年の抱負にしようと思います。
以前のエントリーでも書いたけど、
自分の場合、大学一年の時から常に意識していることがあって、
それを毎年の行動の指針にしている。
(一年生の終わりの期末論文でこの原則を熱く書いたな~そういえば)
それは、自分の「やりたいこと」、「すべきこと」、「できること」、
の3つを念頭において、本当に自分が今すべきことを実行する、ということ。
これは、自分がどんな目標に向かってどこにいて何をしているか、
を認識するのにとても役に立ってきた。
ところで、就活の時に気づいたのだけど、
とある会社もこの3原則を社訓としていた。
俺の方が先だ。
このImayu3原則は常に心に留めておくこととして、
今年は3つの言葉をキーワードに、抱負にしようと思う。
キーワードは、「信頼」、「客観」、「実践」。
①信頼 Trustfulness
今年は、人との繋がりの大切さを心底感じた年だった。その繋がりにいつも助けられたし、迷っている時にも背中を押してもらいました。逆に、大学を卒業する際に、お世話になった先生方に十分な挨拶をせずに帰国してしまった、という悔やまれることがある。加えて、今年からはいよいよ入社ということで、人との信頼関係がより一層大切になってくるはず。
なので、時間のあるこの年、この機会に、今まで不十分だったと思う挨拶などをきっちり済ませ、新たなスタートとしたい。(さぁ~大変だ!)
そして、人から背中を押された分、自分も人の背中を押して上げられるような、そして信頼されるような人間を目指そう。また、信頼構築がより重要になる会社生活を意識して、信頼をむしろ勝ち取るような人間になりたいと思う。
これには、メールだったり手紙だったり電話だったり、細々したことを面倒くさがらずマメにやっていくことが大事だと思うけど、他にもブログであったり、SNSであったり、Web2.0も含めたあらゆる面に敏感になって、自分を発信して相互理解ができればな、と思っています。せっかくミクシィも始めたしね。
②客観 Objectivity
これはImayu3原則の中に既に含まれているけど、自分を客観的に見つめて行動したい、ということ。
2008年は、自分の信念や夢に従って知的好奇心を追求していったぶん、それに熱くなり過ぎて他の事があまり見えなくなってしまったと思う。その結果、自分の考えに確信を持つこともできたけど、そうする内に、そのマイナス面や、逆の視点まで考えが至らないことが多々あった。
マイクロクレジットにしても、マイクロファイナンスにしてもそう。様々な方法で途上国貢献を実現している光景を目の当たりにして心酔してしまい、客観的な視点を欠いてしまった。その度に色んな人にハッとさせられて考えさせられて。
2009年は、これからは、こういうことを無くして行きたい。政治科学を取っていた時、その問題点に気づいて人権学も勉強し始めたじゃないか。日本での留学プレゼンだって、留学生の視点だけで物事を言っていてはダメだと気づいて、日本の大学に潜入調査に行って来たじゃないか。こういう客観的な観点こそが、自分を支えてきたコアだということを忘れていた。
自分の夢を実現する時こそ、大きく環境が変化する2009年こそ、こういう客観的な視点を忘れずに、物事の問題点を冷静に認識して、それを改善できるように努力していきたい。
2009年は絶対に、客観的視点を忘れない!
③実践 Practicality
大きな環境の変化に晒されるであろう2009年、学生時代とは違った実践性が求められるのだろうと思う。特にこれからはビジネスの世界に足を踏み入れるので、学生時代に培ってきた考え方を実践分野にうまく転換していかなければならないと思う。具体的な例で言えば、ビジネスオケージョンにおけるロジカルシンキングとか財経理税務会計とかコーポレートファイナンスとか。
short term goalとlong term goal、その2点を視野に入れて、よく考えて、今すべきこと、できることを明確にして、キチンと実践していきたい。
この3つを今年の目標にしよう。
みんな、もし俺がこれらを怠っていたら、遠慮なく指摘してください。
ブログで宣言してしまったのでもう逃げられないw
具体的な目標、成果はおいおい書いていきたいな。
今年厄年だろうが何だろうが、全力で駆け抜けてやる。
あとは本を沢山読むことと、ドラムやファッションとか他の事にも手を抜かないこと。1~2日に1冊のペースは維持して行きたいし、リラックスして、色んなことにチャレンジして視野を広げていきたい。考え方が凝り固まってしまってもいけない。まず、入社までに、新潮文庫のパンダのブックカバーを2つゲットして。。。
ということで、みなさん今年も宜しくお願い致します。
2009年も、頑張っていきましょう!
Imayu
2009年、同じく厄年の人wあららw→
Calendar
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ichigo-Ichie
Category
Profile
HN:
Imayu
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1985/05/13
趣味:
ドラム・筋トレ・読書・旅行・絵描き・マグカップ収集 etc...
自己紹介:
英語偏差値30の高校時代を経て、カナダ東海岸、St.Thomas Universityに留学。政治科学と人権学を専攻。専門はアフリカ人権問題とドイツ政党政治。2009年4月付けで、某財閥系総合商社へ入社。
先進国に生を受けたからには世界を相手に何か出来る事が、すべき事があるんじゃないか。「『日本人として』、世界という舞台で闘い、途上国の人々の未来を創る」という夢に向かって邁進中。ビジネスを通した途上国貢献の道を模索中。
''Watch your thoughts; they become words.
Watch your words: they become actions.
Watch your actions: they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; for it becomes your destiny.''
※メール→imayu_canada[at]yahoo.co.jp(ブログ用)
先進国に生を受けたからには世界を相手に何か出来る事が、すべき事があるんじゃないか。「『日本人として』、世界という舞台で闘い、途上国の人々の未来を創る」という夢に向かって邁進中。ビジネスを通した途上国貢献の道を模索中。
''Watch your thoughts; they become words.
Watch your words: they become actions.
Watch your actions: they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; for it becomes your destiny.''
※メール→imayu_canada[at]yahoo.co.jp(ブログ用)
Newest
Comments
[07/02 Marcushon]
[07/02 ThomasRese]
[06/22 Hisegar]
Search
Visitors






